小金井自然観察会 コラム
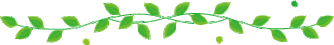
会報「こなら」2025年4月号に掲載
祝!武蔵野公園早朝探鳥会 200回 達成
川崎 道雄(当会副会長)
武蔵野公園早朝探鳥会が2025年1月25日(土)の回をもって、200回を記録しました。
武蔵野公園での早朝探鳥会は、2015年10月3日から始まりました。
会員の渡辺昭彦さんと松村茂生さんが武蔵野公園を中心として、早朝の野鳥観察を行っておられ、いつもその情報をメールでお知らせいただいておりました。
定点における野鳥の出現数の調査をしたいと考えておられた大石会長が、渡辺さんと松村さんの早朝野鳥観察会に相乗りする形で、時間とコースを決めて早朝探鳥会を開始しました。毎月第1と第4土曜日の月2回、4月~10月の時期は6時30分から、11月~3月の時期は7時から1時間としました。早朝探鳥会では、1時間に決められたコースを回り、出現した野鳥の数をカウントしています。

記念すべき第1回目は13名が参加されました。
以降、200回までに75名(会員及び会員外を含む)の方が参加され、延べ人数では1,790名となります。皆さんのおかげで10年に亘って武蔵野公園の野鳥の数の調査が出来ました。ありがとうございました。尚、この間に中止となった探鳥会は22回ありました。
200回の早朝探鳥会で観察した野鳥の種類は49種で総数2万2744羽になります。出現回数が一番多かったのは、ハシボソガラスで200回中200回記録されています。出現率100%です。その次に多いのがキジバトで198回、その次がハシブトガラスとシジュウカラの196回でした。5、6ページに200回探鳥会の集計一覧を掲載しておきますので、ご覧いただければと思います。
200回目の早朝探鳥会に参加された方々(右より、川村宜義、中村純子、鹿島彬世、鹿島克己、大石征夫、松尾義明、長名優子、
有馬祐子、今村志摩、高月響の各位)(2025/1/25、撮影者:松村茂生氏)
2024年10月会報「こなら」に掲載
夾竹桃(キョウチクトウ)
川崎道雄(当会副会長)
6 月 29 日に東京薬用植物園で観察会を行いましたが、薬用植物園にはいろいろな薬に用いられる植物が植えられていました。「薬用」の植物は「毒性」を有する者もあります。「毒」も使い方次第で「薬」になるからです。そこには夾竹桃も植えられていました。大石会長が、夾竹桃の枝や葉っぱには毒性があります、と教えてくださいました。そこで思い出したのは、「ミステリと言う勿れ」というミステリードラマの中で、山小屋の暖炉で夾竹桃の枝葉を燃やし、その煙で人を殺す、という場面です。その話をすると、大石会長は、夾竹桃の毒性が、人を殺すほど強いかどうかは、分からないですね、との感想でした。
それで少し調べてみますと『ミステリと化学』(今村壽明・山崎昶著、裳華房、1991 年)という本の中に、ミリアム・アレン・ディフォードという人が書いた『夾竹桃』というタイトルの推理小説があり、その中で、夾竹桃の枝をバーベキューの串に使って、人を殺す話が有ると紹介してありました。その他に、西南戦争の時に、官軍の兵士が夾竹桃の枝を折って、箸に使って食事をしたため、腹を下した、という話も紹介してありました。この話も大石さんにしましたが、やはり、ちょっと懐疑的でしたので、そこで、知り合いの薬学博士に夾竹桃の毒性について尋ねたところ、下記のような返事がありました。
「夾竹桃の毒性は有名ですよね。夾竹桃の葉5-15枚で死に至るそうです。葉が混入した飼料を食べた牛が死んでいます。牛1匹が食べた葉の量は0.5gほどだったそう。葉に含まれる毒素はオレアンドリンで致死量0.3mg/kgで、フグ毒のテトロドドキシン0.1mg/kg、青酸カリ 150-300mg/kg と比べても、強さがわかります。身近にあるだけに気をつけないといけませんね。」
かなり毒性が強いそうです。うっかり触ったりしないほうがよさそうです。なお、夾竹桃の名前は、花が桃に、葉っぱがタケに似ていて、両方の特徴が混ざっている、つまり「夾雑」しているので、付けられたようです。夾竹桃の基本情報としては、キョウチクトウ科キョウチクトウ属、インド原産(学名:Nerium indicum)。葉は 3 葉で輪生し、幅 1~2センチの細長い(6~20センチ)楕円形。花の形は高坏型で色は白や赤、ピンクなど。
キョウチクトウの仲間は、みんな毒性を有するので、この種の植物を食草とするチョウはほとんどいないのですが、南西諸島に生息するオオゴマダラという大型のチョウは、キョウチクトウの仲間のホウライカガミという蔓性の植物を食草としています。ホウライカガミにも毒性があり、その落葉を家畜が誤って食べて死亡した例もあるそうです。オオゴマダラの幼虫は毒に反応せず、毒素を体内に溜め込んで長期間保持するようです。羽化後の成虫にもホウライカガミ由来の有毒性物質が含まれ、捕食回避に役立っているといわれています。
2023年10月会報「こなら」に掲載
春夏秋冬の木
川崎道雄(当会副会長)
春夏秋冬の「春」の字に「木」扁を付けると、「椿」という漢字になります。
言わずと知れた「ツバキ」です。漢字の故郷の中国では、「椿(chun)」の字は、「香椿(チャンチン)」を指す場合が多いようです。チャンチンは、センダン科の落葉樹です。ほかに「臭椿(チュウチン)」があり、これは「ニワウルシ(シンジュ)」のことです。日本で言うところの「ツバキ」は中国では「山茶」と書
きます。では日本で言うところの「山茶花(サザンカ)」は、中国ではどう書くのかと思いますが、中国語の辞書には「茶梅」と出ています。ただ、「サザンカ」は日本固有の植物で、中国では自生していないようですので、中国で発行している代表的な植物図鑑である『中国高等植物図鑑(全 5 冊)』(北京、科学出版社)
には「サザンカ」は載っていません。ちなみにツバキ(ヤブツバキ)の学名は“Camelia japonica”、サザンカは“Camelia sasanqua”です。
つぎの「夏」に「木」扁を付けると、「榎」になります。「エノキ」ですね。現代の中国ではこの「榎(jia)」という漢字はあまり使わないようですが、「檟(jia)」と同じ意味で、「ヒサギ」を指すようです。では、中国で「エノキ」はどう書くかと言うと「朴樹(poshu)」と書きます。ただ、「厚朴(houpo)」と書くと「ホウノキ」のことになります。
つぎ、「秋」に「木」扁を付けると「楸」になります。「ヒサギ」を意味するそうですが、そもそも「ヒサギ」とは何かというと、どうやら「キササゲ」あるいは「アカメガシワ」を指す古名のようです。中国でも「楸(qiu)」はノウゼンカズラ科のキササゲ属を指すようですが、「楸樹」と書くと「トウキササゲ(Catalp bungei)」のことのようです。「キササゲ(Catal ovata)」は「梓樹(zishu)」と書きます。中国ではこの梓樹を印刷用の版木に利用していて、書物を出版することを「上梓」というのは、ここから出ているようです。日本で「梓(あずさ)」というと、「梓弓」が有名ですが、この「梓弓」が何の木でできていたかは諸説あるようですが、「ミズメ(ヨグソミネバリ)」(カバノキ科)である可能性が高いそうです。ただ標準和名として「アズサ」という名前は、今の植物図鑑には掲載されていないようです。牧野富太郎は、「梓」を「トウキササゲ」としているようですが、前述のように中国では「梓」を「キササゲ」、「楸」を「トウキササゲ」としています。
最後に「冬」に「木」扁を付けると「柊(ヒイラギ)」になります。中国では「柊」の字は古くは別の植物を指していたようですが、近年は「柊(zhong)樹」と書いて「ヒイラギ」を指すようになったようですが、それとは別にヒイラギは「刺葉桂花」とも書くようです。「桂花」は「モクセイ(木犀)」の意味で、「葉
にトゲの有る木犀」ということでしょう。余談ですが、私の生まれた京都の北区にある上賀茂神社の北の方に「柊野(ひらぎの)」という地名があります。当然、ヒイラギが数多く植えられていたからでしょうが、それはきっと、節分にヒイラギを飾るのと同様に、都を悪霊や鬼から守るための魔除けだったと思われます。
さらに余談ですが、手許にある岩波書店発行の『岩波国語辞典』には「椿」「榎」「柊」の文字は載っていましたが、「楸」の字は載っていませんでした(キササゲ「木豇豆」は載っています)。逆に中国で最もポピュラーな漢字字典『新華字典』には、「椿」「楸」は載っていましたが、「榎」「柊」は載っていませんでした。日中の植物に対する親近感が垣間見えるような気がします。
苔(コケ)のお話
川崎 道雄 (当会副会長)
今回はコケの話をしてみようと思います。コケ、漢字は苔や蘚の字を使うようです。
これまでの観察会でコケが記録されたのは、一度だけだと記憶します。2015年12月に小金井公園で「ホンモンジゴケ」をちょっとだけ観察したと思います。池上本門寺で初めて見つかり、その名前が付いたというコケです。銅葺きの屋根から銅のイオンが混ざった雨水が流れ落ちる場所にしか生えないという変わったコケです。小金井公園でも江戸東京たてもの園に入ってすぐのところの屋根の下に生えていたと思います。
ところでコケって何でしょう。「緑っぽくて、じめじめしたところを好み、地を這うように広く生え、岩や樹皮の上にも生える」というような印象でしょうか。俳句では、コケは夏の季語になっていて、ある歳時記には「苔は梅雨のころ、その緑を増し、淡い紫や白の胞子を入れた子嚢(しのう)をあげる。これを俗に苔の花といっている」と記して、「水打てば 沈むが如し 苔の花(高濱虚子)」の句が併記されていました。


コケの特徴を挙げると、種子は作らず胞子で繁殖する、大量の胞子を飛ばすことで生育しやすい環境を探すことが出来る、根(仮根)は、体を地表に固定させるもので、養分を吸い上げることはなく、葉や茎などの表面全体で吸収する、というようなものでしょうか。写真は我が家の近くで見つけたコケです。上の方はおそらく「ハマキゴケ」です。コンクリートや岩の上に生えるそうです。下はおそらく「ゼニゴケ」です。傘のような形のものが見えますが、これは、「雌器床」と呼ばれ、ここで胞子が作られます。二種ともよく見られるコケのようです。今回、コケの話を書いていますが、実は私自身、何も知りません。同じく胞子で増えるシダ類との違いも、よく分かりませんし…。ただ、京都の苔寺をはじめ、庭を彩るコケは緑の絨毯のようで美しいものです。日本には、約千八百種のコケが生息しているそうです(諸説あり)。今の梅雨時は、コケの美しさを知るのにちょうどいい時期らしいので、地面やコンクリートの壁、樹木の幹などに生えているコケに目を向けてみようと思いこの文章を書きました。皆さんもコケをながめてみてはどうでしょうか。
(参考:『じっくり観察 特徴がわかる コケ図鑑』大石善隆、ナツメ社、2019年5月初版)
2021年4月会報「こなら」に掲載
野 鳥 を 食 す
川崎道雄 (当会副会長)
先日、池袋で落語を聞いていたら、そのマクラの中で、「三鳥二魚」という言葉が出てきました。これは、江戸時代に謂われていた五つの「珍味」のことだそうです。「三鳥」(サントリーではありません、サンチョウです)は、鶴(ツル)、雲雀(ヒバリ)、鷭(バン)で、「二魚」は、鯛(タイ)、鮟鱇(アンコウ)のことです。「二魚」はさておき、ツルやヒバリ、バンが好んで食べられたとは、驚きです。
ツルは丹頂のことでしょうか。ただ、『遺伝子から解き明かす鳥の不思議な世界』(一色出版)という本には「丹頂の者は肉硬く、味い美ならず」と古い文書の記述が引用されています。丹頂ではなく、ナベヅルが美味しく、よく食べられていた、とも書かれています。中国で出版されている『中国動物図譜(鳥類)』(科学出版社)には、鳥の解説文の中に「経済意義」という項目が有ります。「経済意義」とは、「利用価値」というぐらいの意味でしょうか。そこの「丹頂<丹頂鶴>」(< >内は中国語の表記)の「経済意義」欄には「常に飼育され、鑑賞に供する」と記載するだけで、食用としての記載は有りません。「ナベヅル<白頭鶴>」は、この本には記載がありませんが、「クロヅル<灰鶴>」は、「珍しい鑑賞鳥。以前は、食用として或いは飾り羽のために捕獲されていた。今、猟は禁止されている」との記載が有ります。ただ、クロヅルは日本では珍しいそうなので、江戸時代に食べられていた可能性は無いかもしれません。江戸時代、ナベヅルは「黒鶴」と呼ばれていたようです。
次はバンですが、バンなんか食べられるのだろうかと思いましたが、池波正太郎氏の『鬼平犯科帳』の第11話「狐火」の中に、「鷭のつけ焼き」を食べる場面があるとのことです。肉をたれに漬けてから焼いたもののようで、かなり美味しいとのことです。『中国動物図譜(鳥類)』には「バン<黒水鶏>」についての記載はありませんが、「オオバン<骨頂鶏(白骨頂)>」は「肉の量は多く、味も良い。南の地方では冬の主要な狩猟の野鳥」と有りますので、オオバンはよく食べられていたかもしれません。
さて、ヒバリですが、これこそ本当に食べていたのかと思いますが、インターネットで調べてみると、なんと「焼き鳥にすると絶品」と有ります。「雲ハツ」と呼ばれて有名のようです。『当流節用料理大全』にもヒバリが食べられていたことが、記載されているようです。しかしかの『中国動物図譜』では、「ヒバリ<雲雀>」は「籠で飼う鳥として名高い」とだけあり、食用については一切触れていませんでした。中国では、食べなかったのでしょうか。そんなはずは、ないでしょうが、鳴き声がいい鳥は、籠に入れて、ほかの人の鳥と鳴き声を競うという遊びが中国では隆盛していたので、そちらに使われて、食されなかったのかもしれません。
「三鳥」という言い方には、別の鳥を指すこともあるようです。『庖丁聞書』には「ツル、キジ、ガンを〈三鳥〉と呼ぶ」と有るそうです。ついでに『中国動物図譜』での記載を見てみますと、「キジ<雉>:肉の味は美味。「野味上品」。羽は装飾用として用いられる」、「マガン<白額雁>:食用に供するが、数が少ないため経済価値は大きくない」、「サカツラガン<鴻雁>:肉量は多く、羽の利用価値も大きい。主要な狩猟鳥」、「ヒシクイ<豆雁(大雁)>:サカツラガンと同等の価値がある」とあります。
随分以前の話ですが、「野鳥」の料理を食べたことがあります。日本橋の或る鳥料理屋で、清水名誉会長と大石現会長と私と三人でカモの「コース料理」を食べました。その料理屋は、事前に予約しておくと、千葉へ狩りに出かけ、マガモを獲ってきて、料理してくれるのです。猟が出来るのは、11月から3月(ところによっては2月)の間で、ひとつの店で捕獲できるのは一日に3羽以内と聞いています。あまりにも美味しかったので「カモ研究会」と称して、機会があればまた食べに来ようと言っていましたが、残念ながら再訪は叶っていません。何時かまた「カモ研究会」を開きたいものです。

2020年10月会報「こなら」に掲載
100 回を迎えた「武蔵野公園早朝探鳥会」
川崎道雄 (当会副会長)
2015 年 10 月 3 日より、武蔵野公園で早朝探鳥会を始めました。観察コースを決めて、種ごとに現れた個体数をカウントしようという試みです。いつも武蔵野公園の定点観察をしておられる渡辺幹事と松村幹事にご協力いただき、コースなどを設定しました。
その探鳥会が 2020 年 6 月 27 日でちょうど 100 回を数えました。切りがいいので初歩的な数字の報告をしておきたいと思います。
100 回の探鳥会で見られた鳥は 67 種類で、個体数の合計は、1 万 6013 羽を数えました。その中を見ていくと、出現回数が 1 回だけというのは、14 種います。
アマツバメ、ヒメアマツバメ、タシギ、サンショウクイ、エゾムシクイ、センダイムシクイ、オオヨシキリ、キレンジャク、
ヒレンジャク、ノビタキ、オジロビタキ、タヒバリ、ベニマシコ、コジュケイです。貴重な出会いだったのですねえ。逆に、毎回見られたというのは、ハシボソガラスだけでした。ハシブトガラス、キジバトは、99 回観察されていますので、見られない日が 1 回だけあったのですね。それ以外に 90 回以上見られたのは、カルガモ、シジュウカラ、ヒヨドリ、スズメのお馴染みの 4 種類です。
総個数で見てみますと、一番数多くの個体が見られたのは、ムクドリでした。
1795 羽。2 番目に多かったのはヒヨドリです。1732 羽。出現回数は、ムクドリが 74 回、ヒヨドリが 97 回ですので、ムクドリが群れで現れることが多いことを物語っています。これ以外に総数が 1000 羽を超えたのは、スズメ、キジバト、
カルガモ、カワラヒワ、シジュウカラの 5 種類です。カワラヒワは、1209 羽ですが、出現回数は 49 回と割合少なく、これも群れで良く見られたことが分かります。渡り鳥の中では、出現回数が 51 回、個体数が 928 羽のツグミが、一番でした。特徴的なのは、アトリが出現回数 8 回で、なんと 574 羽を数えています。
今回は、節目の 100 回を迎えた早朝探鳥会の基本的な記録をご紹介しました。
ご参考までに、観察された野鳥の一覧を 7 頁に掲載しておきます。今後は、さらに記録を積み重ね、季節ごとの鳥の増減や種類の傾向などを反映するような数字を出せるようにしたいものです。
これまでの参加者は、会員が 27 名、一般の方がのべ 9 名参加されています。
1 回の参加者数は平均で 7 名です。これからも多くの方が参加されることを願っています。早朝探鳥会のページ
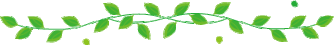
ものぐさバードウォッチング カラス・ハト・スズメ篇
川 崎 道 雄 (当会副会長)
野鳥は詳しくないという方でも、カラスやハト、スズメ、というと何となくその姿がイメージできると思います。私がこの会に入って間もない頃、清水徹男先生(現名誉会長)から、なじみの深いカラス・ハト・スズメの識別こそ、しっかりやりましょうと言われました。その言わんとするところは、カラス・ハト・スズメが確実に見分けられると、フィールドでカワラヒワに出逢ったとき、カワラヒワという鳥は知らなくても、これはスズメではない、ということが判断でき、それではなんという鳥だろうか、チョウゲンボウを見かけたときにも、これはハトではないな、と分かればその先へ進むことが出来るというのです。
カラス・ハト・スズメと書きましたが、小金井市内で見られるカラス(と皆さんが認識する黒いカラス)は、ハシブトガラスとハシボソガラスが見られます。「カラス」という名前(標準和名、種名)のカラスはいません。ハトも、「ハト」という名前のハトはいません。小金井ではキジバト・カワラバト(ドバト)が見られます。スズメは、一般名詞としても種名としても使われています。小金井で見られる「スズメ」はスズメという種名のスズメ1種だけです。ニュウナイスズメというスズメの仲間がいます。一度、埼玉県まで会として見に行ったことがあります。
さて、ではカラス・ハト・スズメとはどんな特徴があるのでしょうか。ハシブトガラスとハシボソガラスはその名の通り「ハシ」(嘴(くちばし))が太いのと細いのとが特徴です、といわれても実際には迷うことが多々あります。「ブト」はおでこが出っ張っているとか、体は「ボソ」の方が少し小さいなどとも言われますが、これも野外ではわかりにくいものです。一番わかりやすいのは鳴き声です。「ボソ」は「グヮー、グヮー」と濁った声で、「ブト」は「カァー、カァー」と澄んだ声です。鳴くときに首を上下に振るのは、「ボソ」です。歩き方では「ボソ」はテクテクと歩き(ウォーキング)、「ブト」はピョンピョンと歩く(ホッピング)ことが多いと言われます。
キジバトとドバトの識別ですが、キジバトの色は全体的に茶褐色の印象があります。翼に鱗のような模様があり、襟首(でいいのかな)の両側に網目模様があります。ドバトの色は、伝書鳩でおなじみの色模様や、白、茶色などいろいろです。鳴き声は、キジバトが「デデポー」、ドバトが「クックルー」と表現されます。群れるのがドバト、単独ないしペアで行動するのがキジバト、とも言えます。
スズメの特徴は、「チュンチュン鳴いている」「一見して茶色っぽい」「(小さい鳥が)5羽以上に群れて電線・屋根にいる」、このうちの1つでも当てはまれば、ほぼスズメ、3つ揃ったら完全にスズメだと言えるそうです。
カラス・ハト・スズメは、市街地でも普通に見られます。ものぐさバードウォッチャーとしては、恰好の対象です。街角で「カラス」を見かけたら、あれは「ブト」かな、「ボソ」かな、と識別をしましょう。「ハト」ならキジバトかな、ドバトかなと見て歩くと、散歩の楽しみが増えます。

ハシブトガラス

ハシボソガラス
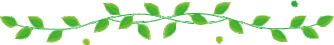
ものぐさバードウォッチング:小説篇
川 崎 道 雄 (当会副会長)
読書をしていると――特に小説や物語を読んでいると、「大川の岸辺に数羽のタマシギがいる」というような一節に、急に出会うことがあります。それは、まるで野川を散歩していて、いきなりタマシギと出会ったかのような喜びの感情を与えてくれます。小説でもバードウォッチングができる、と信じる由縁です。
しかし、私の経験からしますと小説などに出てくる鳥の名前と言えば、カラスでありハトでありカモでありサギです。種名としてのハシブトガラスもキジバトもカルガモもダイサギもほとんど出てこないのが普通です(ツバメ、スズメは一般名詞と種名とが一致しているので種名が書かれることが多い野鳥と言えますが、書いた作家は種名であると意識することは少ないかもしれない)。
そもそも小説に野鳥が出てくるということは、すべて、作家の好き嫌いや小説の筋に何らかの関わりの有る無し、つまり作家の思惑・考え方一つにかかっています。まあそれは当たり前のことで、野鳥に興味のない(と思われる)作家の小説では、ほとんど野鳥とは出会えません。
宮沢賢治の「よだかの星」のような登場人物(鳥物?)が野鳥ばかりの作品は置くとして、野鳥と出会う確率が高いと思うのは、私が還暦を過ぎてから読み始めた藤沢周平のいくつかの作品です。
同氏の時代小説で、山形地方にある(と思われる)藩を舞台にした作品などでは、夏の夜、見張りをしている侍の頭上をよく夜鷹(ヨタカ)が飛ぶのです。夏の場面になると、郭公鳥(カッコウ)が鳴きます。また、ある場面では、「……時おり小さなしぶきを立てる水鳥の姿が見えるほどである。鳥は鷭(バン)か、あるいは夏も残る鴨かもしれなかった」とあり、バンかカルガモかと思われる表記があり、その後の文章「対岸の葦の間で黒い鳥が飛沫をあげる」で、おそらくバンだとわかります(以上は『隠し剣孤影抄』より)。「風景は日日灰色に、初冬の気配を帯び始めていた。その風景の上を、群れを成して鶸(ヒワ)が飛ぶ日もあった」の鶸は、マヒワであるかもしれない(『麦屋町昼下がり』より)。物語に引き込まれている時にふっと野鳥が現れると何か心を衝かれるような印象深さを覚えてしまいます。
ところで、冒頭で紹介しました「タマシギ」ですが、どの作品に出ていたかを思い出せなくなってしまいました。ぱっと思いついたのは、久保田万太郎の『春泥』でしたが、この文章を書くにあたって本を繙いてみましたが、そんな記載は見つかりませんでした。どこかで「タマシギ」に出会ったのは確かですが、どの小説のどの辺かがまったくわからなくなってしまったのです。ことほど左様に、野鳥の観察記録は重要であることを思い知った次第であります。今後、小説で野鳥に出会ったら、かならず種名とタイトルとページ数を記録しておくことをお勧めします。そして、ほかの人に教えてあげてください。実際のバードウォッチングでは、いついつ、どこどこでこんな鳥を見たよ、と聞かされても、後日その場所でその鳥が見られる保証はなく、悔しい思いをすることもありますが、小説であれは、それは必ずほかの人も見ることが出来るからです。(会報 こなら 2017 年10 月1日号に掲載)
